日本の食文化を彩る「イカ」/さかなの日
石川県の味覚を代表する四季の魚のなかで、「夏の魚」に定められている「イカ」。
夜の海に揺れるイカ釣り船の漁火は能登の夏の風物詩です。
多くの種類のイカのなかから日本の食卓にとてもなじみの深いスルメイカをご紹介いたします。

「イカ」は「カイ」?!
私たち日本人にとって、とても身近な食材であるイカ。実は貝類の仲間なのを知っていますか?たとえば、イカの甲の部分や、薄い軟骨のようなもの、あれは正確には「貝殻」なのです。
そんなイカは、胴の中に硬い甲をもつコウイカ目と、細長い体をもつツツイカ目に大別でき、世界中には、約450種類前後が生息しています。コウイカ目には5科、ツツイカ目には28科の計33科が属し、そのなかでもコウイカ科、ヤリイカ科(ジンドウイカ科)、スルメイカ科(アカイカ科)の3科に、私たちが食用としてなじみ深い種類は、ほぼ属しています。
舟形の甲をもつのが特徴のコウイカ科に属するイカには、コウイカやシリヤケイカ、カミナリイカなどがいます。コウイカは、釣り上げたときに大量の墨を吐くところから、「墨イカ」とも呼ばれています。
ヤリイカ類では、先がヤリのようにとがっているヤリイカや、もっともおいしいイカといわれるアオリイカが有名です。
そして、これらイカの中でとてもポピュラーなのが、スルメイカ類の代表、ご存知スルメイカ。日本近海に広く分布し、イ力の乾燥品である「するめ」の多くは、このスルメイカから作られます。
能登で多くのスルメイカが漁獲されている、集魚灯と自動イカ釣り機を使用したイカ釣り漁業。複数の漁船が船団を組み、一斉に漁に出ます。そして夜間にスルメイカを集めて漁獲するために集魚灯を点灯します。この灯りが、陸地から見ると大変美しく幻想的な「漁火」です。

イカは栄養バランス◎!
噛めば噛むほど味わい深いイカ。イカの深いうまみは、甘味成分であるアミノ酸を多く含んでいるためです。また、消化作用を助け、コレステロールを下げる働きがあるタウリンも豊富に含んでいます。するめの表面に出る白い粉にはそのタウリンが凝縮されています。
イカは噛み応えがあるために、消化されにくい食品と思っている人もいるようですが、イカの消化率は実は他の魚類と同程度。かつ、イカの脂肪含有量は約2%で、魚介類の中でも少なめ。また、量は少ないもののビタミンD以外のビタミン類をほとんど含有しており、バランスよくビタミンを摂取することができるのです。とくに、イカの中でも内臓ごと食べるホタルイカは、ビタミンAとEをたっぷり含んでいます。
このように、おいしくて栄養バランスのよいイカは、食生活に積極的に取り入れたい食材です。

みんな大好き!イカの加工品
イカはさまざまな料理に使われるのはもちろん、塩辛をはじめとした珍味や調味加工品に加工されています。
たとえば石川県には、イカの内臓からつくった「いしり」という魚醤や、そのいしりに地元のイカを内臓ごと漬け込んで乾燥させる「もみいか」という伝統食品があります。もみいかは、乾燥時にイカを芯まで脱水させるため、ワ夕(内臓)までおいしく食べられます。炙ってぜひお試しいただきたい逸品です。
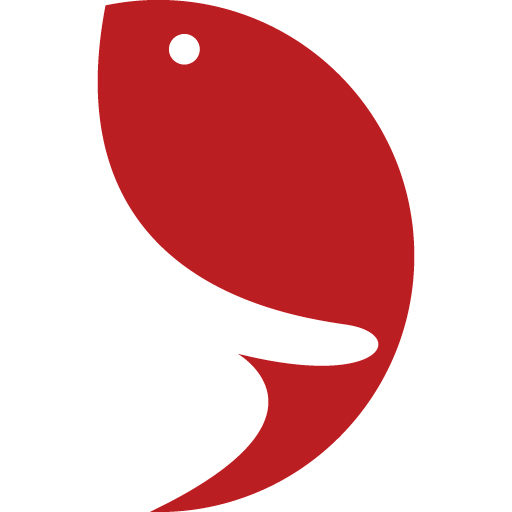
イカの旨味を丸ごと味わえるもみいかは、ワタのほろ苦さが絶品!
酒の肴に最適です♪
能登の美味しい“もみいか”が入っている商品はこちら


